回答する側と確認する側、双方の負担が軽減されました

| 課題 |
|
|---|---|
| 決め手 |
|
| 効果 |
|
当院は高崎・安中医療圏で唯一の三次救急医療機関であり、救急医療と急性期医療を中心に地域の医療を支える総合病院です。従業員の規模としては、常勤非常勤含めて千人あまりの職員が勤務しています。
| お話を伺った方 |
国立病院機構 高崎総合医療センター
|
他の同系列の病院から「『安否コール』が便利だ」という評判を聞き、導入を決めました。
安否確認システムを導入するきっかけを教えてください。
平塚 様
今までは電話を使い緊急の連絡網での確認を行っていましたが、確認に時間がかかっていたことがありシステムの導入を検討しました。
導入の検討をする際、他社製品との比較をされたようですが、「安否コール」を採用した理由となるポイントは何かありますか?
平塚 様
当院は国立病院機構の系列となる病院で、全国各地に多くの系列病院があります。 [他の国立病院機構系列の病院で多数、「安否コール」の導入事例があることや、「安否コール」は非常に便利だということを、当時の担当者が聞いていたりしたそうです。]また、院内で災害関係に取り組んでいる職員も「安否コール」を知っていたこともあり、「安否コール」の導入を決めたと聞いております。
操作面で迷うことはなく、わかりやすくてスムーズです。

新しい職員さんが入職したときに、どのような登録のご案内をされていますか?
平塚 様
入職する前に、必要書類と一緒に「安否コール」のアプリをダウンロードするQRコードを貼った、簡単な登録のフローチャートを書いた紙を同封し、「入職するまでに登録してください」という案内を送らせていただいております。
そのときに「登録が難しい」とか「登録できない」といったお問い合わせはありますか?
平塚 様
入職する方からは今のところ、ダウンロードするまでに何か困ったとか、そういったお話を聞いたことはありません。職員の登録に関して管理者の手間はほとんどかかっていないと思います。
新たに入職される方が登録した後にテスト配信はされていますか?
平塚 様
今年度になって全体でのテスト配信は行っておりませんが、各部署単位で配信テストを定期的に行っております。
異動や退職される職員さんもいらっしゃると思います。そういった場合のメンテナンスはどのようにされていますか?
平塚 様
異動や退職があった場合は、管理画面から削除しています。基本的にはCSVなどは使わず、個別に操作して対応しています。
操作面で問題はありますか?
平塚 様
操作面では迷うことはなく、わかりやすくてスムーズにできています。
入職時と退職時のフローというのは確立しているということですね。
平塚 様
はい。日頃の運用としては、ある程度固まっていると思います。
全体での配信訓練について教えてください。
平塚 様
今年度は今のところ各部署単位で行っておりますが、個別でのテストだけでなく全体でのテストもやっていけたらと思います。
確認する側と確認される側、その双方の負担が軽減されたのがメリットと思います。
今後のお話を伺えればと思います。今後、「こういうことをやっていきたい」とか、目標としていることはありますか?例えば、直近で防災訓練をするような計画というのはありますか?
平塚 様
災害訓練は予定しておりますが、そこに「安否コール」を組み込むところまではできていないので、全体での「安否コール」の配信訓練を行えたらと考えています。実際の災害が起きた時、スムーズに運用ができるのか、目標としてはそういったところになるかと思います。
訓練というのはすごく重要になってくるかと思いますので、ぜひ、お試しをいただければと思います。
他に何かお困りのことや、課題に思っているところはありますか?
平塚 様
現状、困っていることはありませんが、平日の日中帯であれば普段操作している職員が配信などをある程度できると思う反面、休日や夜間の場合に「普段から操作している職員がいない時、スムーズに配信などができるか」というのが不安なところでもあります。これについて、操作方法の周知に今後取り組んでいく必要があると考えています。 操作のマニュアルなどは関係者に配布しているのですが、幸いにも実際に使う機会がまだ起きていないので、実際に操作している職員が少ないというのが課題であると思っています。
令和6年能登半島地震で、御院からも医療チームが出動して被災地の支援をされたそうですが、詳しくお話をお聞かせください。
平塚 様
班単位ですと4班、人数では20名ほどが出動しました。個別に一人単位で向かった職員もいました。災害対応の専門的な訓練を受けたメンバー、いわゆる「DMAT」が、当院の場合は群馬県ですが、県からの出動の要請を受けて、当院から派遣しました。また、当院は国立病院機構という組織ですので、その本部からの要請でも、今回の被災地である能登半島へ出動しました。
出動要請があったときに院内のドクターや看護師、職員等のチームのメンバーに対しての連絡というのは電話で指示される形でしょうか?
平塚 様
出動要請があったときというよりは、災害が発生したとき、LINEのグループを作っていますので、電話やLINEで情報共有しながら、派遣をするのか、できるのかといった調整を図っています。
今はLINEでの運用が浸透してると思いますが、大規模な災害時にLINEがつながらなくなるなどしたときにどうするのかというところも予測をしておく必要があります。 「安否コール」は規制が比較的かかりにくいといわれているWEBを利用したコミュニケーションができるシステムですので、「安否コール」の掲示板をDMATのグループ用に作成しておくなどすると今後さらに盤石の体制になるのではないかと思います。必要でしたら使い方のご案内もさせていただきます。
平塚 様
実際に災害が起きて千人近くいる病院の職員、それに加えてそれぞれの家族までの安否確認を電話で行うとなると、かなりの時間がかかると思います。災害が起きている時に、連絡網で次々回していくとは言っても、「次の人がつながらなかったらそのまた次」のようにかけ続けていくというのは、電話をかける側の負担がかなり大きいと思います。「安否コール」を導入したことで、一斉配信機能を使えば、全体に安否確認の通知が行き届くスピードは電話よりもはるかに早いと思います。 また災害時は必ずしも電話に出られるとは限りません。少し落ち着いたタイミングや、大丈夫だなと思えるタイミングで回答できる点が「安否コール」のシステムで安否確認を行う一つの利点だと考えます。 回答する側と回答を確認する側、その双方の負担が軽減されることが大きなメリットです。
本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。
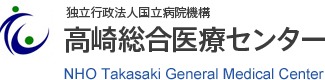
| 社名 | 国立病院機構 高崎総合医療センター |
|---|---|
| 診療科 | 総合診療科・内科 / 脳神経内科 / 呼吸器内科 / 消化器内科 / 心臓血管内科(循環器) / 小児科 / 精神科 / 消化器外科 / 乳腺・内分泌外科 / 呼吸器外科 / 心臓血管外科 / 脳神経外科 / 整形外科 / 形成外科 / 産婦人科 / 泌尿器科 / 皮膚科 / 眼科 / 眼形成眼窩外科 / 耳鼻咽喉科頭頚部外科 / 歯科口腔外科 / 放射線診断科 / 放射線治療科 / 救急科 |
| 利用規模 | 1200名 |
| サイト | https://takasaki.hosp.go.jp/ |
| 業種 | 医療・福祉 |
|---|---|
| 課題 | 安否確認の手段を探している |
上場企業をはじめ1,300社を超える豊富な実績!
さらに徹底分析した詳細な安否確認システム比較表もご用意しておりますので、
採用時の稟議資料などとしてお役立てください。




